認定経営革新等支援機関とは?|取得を迷っているあなたへわかりやすく解説!
中小企業支援に関わったことのある人なら、おそらく一度は聞いたことがある「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」。
興味はあっても「どんなメリットがあるの?」「実際どうやって取得するの?」と疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「これから取得を検討したい」という方向けに、制度の概要、メリット・デメリット、認定要件、申請から取得までの流れ、必要な費用・期間について、認定経営革新等支援機関の登録を受けている行政書士の視点で丁寧に解説します。
認定経営革新等支援機関とは?
中小企業庁が定める「中小企業支援を行うための専門家(士業・金融機関・コンサルなど)」を公的に認定した制度です。正式には「経営革新等支援機関に係る認定制度」と呼ばれ、中小企業・小規模事業者の経営改善や事業計画策定等を、一定の知識と経験を持った専門家が支援できるようにする仕組みです。
平成24年8月に創設されて以降、多くの税理士・中小企業診断士・行政書士・金融機関等が認定を受け、経営支援の最前線で活動しています。
主なメリット
- ① 各種補助金・支援制度に対応できる
「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」など、認定支援機関の関与が必要な補助金申請に対応可能になります。
※現在は事業再構築補助金は終了しましたが、認定支援機関が関与しないと申請ができない補助金だったため、認定支援機関の登録を受けている専門家はニーズが非常に高い状況にありました。私は当時、認定支援機関の登録を受けていなかったので、登録を受けている公認会計士の先生と一緒に補助金サポートをしました。 - ② 信用力・差別化につながる
中小企業庁による公的な認定は、顧客や金融機関にとって安心材料となり、同業他者との差別化にも効果的です。財務・資金繰りの専門家として仕事を受注しやすくなると言えます。 - ③ 顧客単価アップ・継続契約につながる
認定経営革新等支援機関の登録を受けた方が、専門家として顧客単価のアップはしやすいです。中長期の顧問契約にもつながる可能性もあります。
デメリット・注意点
- ① 更新が必要(5年ごと)
一度認定を受けても、5年ごとの更新が必要で、実績や研修状況がチェックされます。
ただ、5年というの期間はかなり長いと言えます。 - ② 責任ある立場になる
より専門的な立場に立つため、専門家として責任のある立場で対応する必要があります。 - ③ 実績や知識の裏付けが必要
補助金制度や経営分析の知識、実務経験が求められるため、準備なしでの参入は難しいです。
認定を受けるための要件
以下のような要件を満たす必要があります。
- ✔ 資格・所属団体など
– 税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士、弁護士
– 金融機関(銀行・信金など)
– 商工会・商工会議所など - ✔ 専門性・実務経験
中小企業支援に関する一定の実務経験や、財務分析・経営診断の知識が必要です。
詳しい要件については、以下の経済産業省のホームページからご確認ください。
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/nintei_shienkikan/shinki_shinsei.html
認定までの流れ
認定経営革新等支援機関の認定(登録)を受けるまでの流れは、実務経験があるか・ないか、所有資格によっても大きく変わりますので、前述の経産省のURLからご確認ください。
ちなみに私自身は、行政書士の資格を持っていて、補助金申請サポートを何件もしたことがあったため、それらが実務経験としてみなしてもらうことができました。
※実務経験が一切ない人は、理論研修と実践研修という2つの研修受講が必要なのですが、私は理論研修だけ受講して、実践研修は受講せずに実務経験で登録を受けました。
費用と日数の目安
これもご自身の実務経験や所有資格によって異なりますので、前述の経産省のURLからご確認ください。
どんな人におすすめ?
- 補助金支援業務を拡大したい士業
- 経営支援を専門にしたいコンサルタント
- 顧問契約の幅を広げたい方
- 金融機関との連携を深めたい方
Q&A
- Q1:行政書士でも取得できますか?
はい、可能です。 - Q2:取得すれば自動的に仕事が増えますか?
いいえ。取得はあくまでスタートライン。営業力と実務力が必要です。 - Q3:法人事務所でも申請できますか?
可能です。個人・法人どちらでもOKです。
認定支援機関は補助金申請のみならず、強力なブランディングにもなる
私自身、認定経営革新等支援機関の登録を受けるのを2年間くらい迷いました。
理由は、理論研修を受講するのに約8万円の受講費用と、約16日間の理論研修の受講が必須だったことです。
※4か月連続で、1か月あたり連続する4日程度の理論研修を受講する必要があります。
別に自分で、認定経営革新等支援機関の登録を受けなくても、他の人に依頼すればいいと考えていました。
ただ、認定経営革新等支援機関の先生と一緒に仕事をするとなると、その先生のスケジュール調整も必要になるし、業務への考え方もすり合わせる必要があったりして、実際はなかなか仕事がしづらかったりします。
自分自身が認定支援機関の免許を持っていれば、自分のスケジュールで自由に仕事がしやすいです。
取得しないといつまでもモヤモヤと迷った気持ちが続いてしまうと思ったので、暇になって時間が取れるようになったタイミングで取得することを決めました。
取得後、補助金申請サポートで認定経営革新等支援機関の資格を使用したことは1回もありません。
ただし、現在M&Aに近い仕事に関わっており、新規事業のリサーチや、小規模企業の買収検討、新規事業の収益プラン作成の仕事をしています。
大口の投資家の方からお誘いいただいたのも、私自身が認定経営革新等支援機関の登録を受けていて、中小企業まわりの数字に強い・よく勉強しているという評価をしてもらえたからだと思います。
その意味では、補助金申請の仕事はしていませんが、事業買収の仕事に誘われるようになったので、中小企業支援の専門家としてのブランディングという意味で取得は大いに意味があったと思います。
※取得してしばらくは、取った意味あったかな?と正直微妙に思ってはいました。
自分が予想外の形で、認定経営革新等支援機関の資格が活用できるようになりました。
なので、ご自身の将来の可能性を広げるという意味でも取得は価値があると思います。
※将来希望するキャリアや価値観にもよりますが


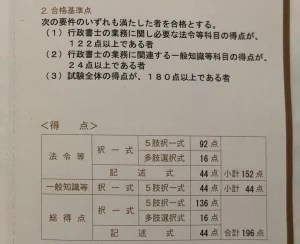

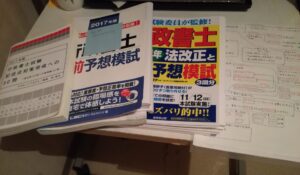
コメント